妊娠・出産にはたくさんの喜びがある一方で、「お金の不安」もつきものです。
そんな不安を抱える方のために、2024年に出産した現役看護師の私が、リアルにかかった費用と実際にもらったお金をすべて公開します!
これから出産を迎える方の安心材料になれば嬉しいです。
妊娠が分かったとき、一番悩んだのが職場への報告タイミングと伝え方でした…。
私の経験をまとめた「看護師の妊娠報告と働き方」の記事もぜひご覧ください。
👉 看護師の妊娠報告のタイミングはどうする?伝え方・夜勤について
妊娠中にもらえるお金・使える支援制度一覧

1. 妊婦健康診査の助成
概要:妊娠中に必要な定期検診(妊婦健康診査)の費用を自治体が助成。
内容:妊娠週数に応じた検査費用の一部または全額を負担。
申請方法:妊娠届を役所に提出すると、母子手帳と一緒に検診費用補助券が配布されます。
2. 出産手当金(勤務中の方のみ)
概要:健康保険に加入している場合、産休中に給与の一部が支給。
支給額:標準報酬日額の2/3相当額。
支給期間:出産予定日を含む42日間(多胎妊娠の場合98日)から産後56日まで。
申請方法:勤務先や健康保険組合を通じて申請。
3. 傷病手当金(勤務中の方のみ)
概要:妊娠中の体調不良で働けない場合、一定の条件を満たすと支給。
支給額:標準報酬日額の2/3相当額。
対象期間:休業4日目から最長1年6カ月。
申請方法:医師の診断書を添付して健康保険組合に申請。
4. 医療費控除
概要:妊娠中の検査費や医療費は、一定額を超えると確定申告で控除可能。
控除対象:分娩費用や通院の交通費も含まれる場合あり。
注意点:検診費用補助券で賄われた分は控除対象外。
5. 自治体独自の支援金
概要:地域によって、妊娠・出産を支援するための独自助成や祝い金が用意されている場合があります。
出産を機に「臍帯血保管」を検討される方も増えています。
実際に私が調べた臍帯血保管のメリット・費用についてまとめた記事はこちら↓
👉 臍帯血保管はすべきか?口コミと医療者夫婦の出した結論
出産後にもらえるお金・制度まとめ
1. 出産育児一時金
概要:出産にかかる費用を補助するための制度。
支給額:50万円
※産科医療補償制度に未加入の施設で出産した場合は48.8万円。
申請方法:健康保険を通じて「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用することで、医療機関への支払いが軽減されます。利用しない場合は、出産後に請求。
2. 育児休業給付金(勤務中の方のみ)
概要:育休中に給料の一部が雇用保険から支給される。
支給額:
育休開始から6カ月:休業前賃金の67%。
6カ月以降:休業前賃金の50%。
支給期間:原則として子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)。
申請方法:勤務先を通じて申請。
3. 児童手当
概要:子どもの養育を支援するため、0歳から中学卒業まで支給される手当。
支給額:
0~3歳未満:月額15,000円。
3歳~小学生:月額10,000円(第3子以降は15,000円)。
中学生:月額10,000円。
※所得制限を超える場合は、一律月額5,000円。
申請方法:出生届を提出する際、役所で手続きを行います。
4. 医療費控除
概要:出産に伴う費用(分娩費用、入院費、交通費など)は医療費控除の対象になる。
控除対象例:妊婦検診費、無痛分娩の費用、助産師の費用。
申請方法:確定申告時に医療費明細書を提出。
5. 自治体独自の出産祝い金・助成金
概要:地域によって、出産を祝して現金や物品の支給、または助成金が用意されている。
例:
出産祝い金(数万円~数十万円)。
育児用品の購入助成券やベビーベッドの無料貸し出し。
子育て支援サービスの無料利用券。
6. 母子家庭向けの支援金(該当する場合)
概要:シングルマザーや低所得世帯向けの特別手当。
例:
児童扶養手当:第1子42,140円、第2子5,000円、第3子以降1人につき3,000円(所得により減額あり)。
自治体独自の母子支援金。
7. 産後ケア事業の助成金
概要:産後の母親や赤ちゃんの健康管理を支援するためのサービス。
内容:
専門家による育児指導や相談。
宿泊・訪問型のケアの費用助成。
申請方法:自治体窓口で手続き。
8. その他の支援制度
子どもの医療費助成:多くの自治体で、子どもの医療費(通院や入院)が無料または一部負担で済む制度があります。
ベビー用品支援:自治体やNPOによる無料配布や貸し出し。
多くの支援金は申請が必要です。
出産前に手続き方法を確認しておきましょう。
【体験談】2024年出産で「かかった費用」と「もらえたお金」内訳
妊娠32週から有給休暇と産前休暇を利用し、東京の実家に里帰り。
その際にかかった費用を公開します!
地域や産院による違いや実際にかかった金額を知る参考になれば嬉しいです。
妊娠初期(母子手帳取得まで)
- 支出:初診+証明書 約5,000円
- 受けた支援
- 妊婦健診クーポン14回分
- 出産応援ギフト(自治体)50,000円
妊婦健診(〜32週/九州)
支出:クーポン利用で実質0円
妊婦健診8回目~12回目まで(里帰り先の産院)
| 妊娠週数 | 健診回数 | 費用 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 33週 | 8回目 | 15,000円 | 採血 エコー検査 |
| 35週 | 9回目 | 24,970円 | 無痛分娩の事前検査 (採血・心電図・エコー検査・膣分泌物検査) |
| 36週 | 10回目 | 7,400円 | エコー検査 |
| 37週 | 11回目 | 7,810円 | エコー検査 NST(ノンストレステスト) |
| 38週 | 12回目 | 7,400円 | エコー検査 |
・支出:合計62,580円

里帰り出産だったためクーポン券は使用できず、全額支払いました。
産後市役所に払い戻し用の申請用紙と検査結果提出しました!
・もらったお金
産手当金(産休手当) 給料日に支給
標準報酬日額の2/3相当額となっていましたが
実際1か月の手取り給料より若干多く振り込まれました!
(厚生年金と健康保険が免除されたため。)
・妊婦検診費払い戻された金額
29.440円
計画無痛分娩~退院
- 支出
分娩・麻酔・個室代など合計794,000円 - 支援
- 出産育児一時金:500,000円(直接支払制度)
- 出産産手当金(産休手当) 給料日に支給
産後1か月健診 自費
支出:母子で9,500円(保険適用外)
産後もらえるお金
- 子育て応援ギフト:50,000円(条件クリア)
- 児童手当:15,000円/月
- 育休給付金:産後4カ月後に初回振込

入金がない期間が4か月あるのがつらかった・・・
みるみる残高が減っていって凹みます。
医療費控除での還付
確定申告で約3万円還付されました!

申告忘れは「更正の請求」で取り戻せる!
ちなみに我が家は、夫が確定申告したので、
還付金は夫の懐へ・・・・・
出産費用の収支まとめ(リアル体験)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総支出 | 871,080円 |
| 総支援額(現金・補助) | 629,440円 |
| 自己負担差額 | -241,640円 |
※育休手当・児童手当・医療費控除の還付金は上記に含まず。
節約志向のママさんへ
赤ちゃんとの生活で、毎日使う消耗品といえば「おしりふき」。
うちはかなり消費量が多かったので、ふるさと納税でまとめ買いできて本当に助かりました!
👉 [おしりふきのふるさと納税はこちら]
必需品だからこそ、人気の返礼品!
はやめにチェックしておきましょう!!
地域差に注意!第一子との比較から見えたこと
第一子のときは、自治体の手厚い支援により約7万円のプラスでした。しかし今回は、里帰り出産で助成が効かず約24万円の赤字に。出産費用は「地域」「産院」「分娩方法」によって大きく変わります。
出産でもらえるお金のシミュレーションはこちら!
出産でもらえるお金の目安を計算できる便利なサイトです。
✅ 出産前に費用のシミュレーションをしておくのが超重要!
まとめ|申請しないともらえない!妊娠・出産のお金のリアル
妊娠・出産には大きなお金がかかる一方で、活用すべき公的支援制度がたくさんあります。
- 制度の多くは「申請しないと受け取れない」
- 自治体ごとに支援内容や助成額が異なる
- 出産スタイルや地域で費用が大きく変動
✅ 計画的に申請・情報収集しておけば、安心して出産を迎えられます!
この記事が、金銭面での不安を減らし、より安心できる妊娠・出産ライフの助けになれば幸いです。
出産に向けてのお金の不安や準備は尽きませんが、少しずつ情報を整理すれば安心につながります。
もし職場での妊娠報告に悩んでいるなら、こちらの記事も参考になると思います↓
👉 看護師の妊娠報告タイミングと注意点
(内部リンク)
また、出産をきっかけに臍帯血保管を検討している方にはこちら↓
👉 臍帯血保管の費用・メリットまとめ
(内部リンク)
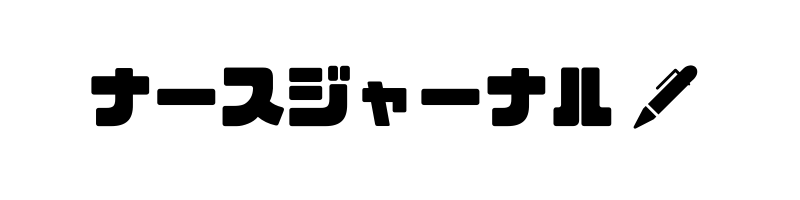

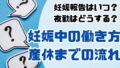
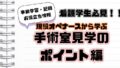
コメント